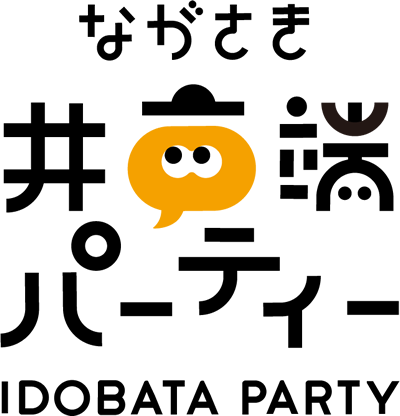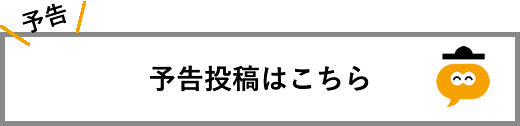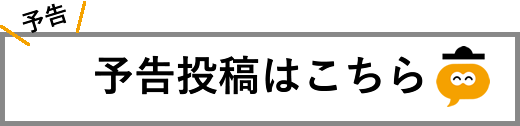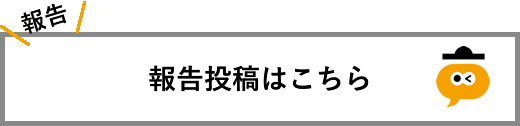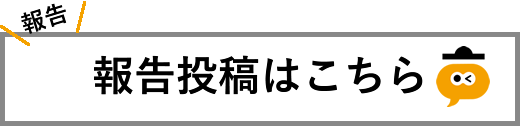2025年07月23日
「ストーリーテリング」を通して広がる「ものがたり」の世界 おはなし魔女の会 代表 平野妙子さん
ながさき井戸端パーティーを活用しているかたをご紹介する「井戸端people」。今回は、日本や世界の民話や創作物語などを暗記して、語りのみで聴衆に伝える「ストーリーテリング」に取り組む「おはなし魔女の会」代表の平野妙子さんにお話を伺いました。

―ストーリーテリングについて具体的に教えてください。
ストーリーテリングは「朗読」や「読み聞かせ」とは異なる伝え方で、あらかじめ丸ごと覚えておいた物語を、本を見ずに、語りだけで伝える手法です。文字で書かれた「物語」は、語りを通して、生き生きと立体的に動き出します。私たちは、そうした語りによって広がっていく世界を「ものがたり」や「おはなし」と、ひらがなで表しています。
語り手が目を見ながら語ることで、聞き手は、まるで自分に語りかけられているような感覚になってより想像が膨らみます。一方、語り手も、聞き手の反応や心の動きを感じながら語りにより気持ちが入っていきます。語り手と聞き手が共鳴することで、お互いが「ものがたり」の世界にどんどん引き込まれていく、、、これがストーリーテリングの魅力です。

―ストーリーテリングを始めたきっかけは?
高校生の時、学校の先生からの紹介で「長崎子どもによい本を!の会」の活動に参加し、そこで、「東京子ども図書館」でストーリーテリングを学ばれた先生に出会ったことがきっかけです。初めて先生の語りを聞いた時は「こんな伝え方があるんだ」と驚きました。もっと学びたいと思い、仲間とともに毎月1回、長与町にあった先生のご自宅に通うようになりました。参加者は徐々に増えていき、やがてその会は「長崎おはなしの会」と名付けられました。私が社会人になった頃、諫早市内から通っていたメンバーが「諫早おはなしの会」を立ち上げたことを知り、先生にご相談のうえ、長崎市内から通っていた3人で2002年に「おはなし魔女の会」を立ち上げました。
―「おはなし魔女の会」の名前の由来は何ですか。
世界各地の物語に登場する「魔女」はさまざま。優しい魔女やおっちょこちょいの魔女もいます。同じように色んな個性を持つ私たち。魔法の力は持たないけれど、「おはなし」という魔法で、子どもだけではなく大人にも、夢や希望、勇気を届け、幸せになってほしいという想いから名付けました。
「おはなし」を聞くことで、子どもは想像力を育み、自分を物語の主人公に重ね合わせながら、自ら考える力、困難を乗り越えていく力を身につけていくことができます。大人も、自由に想像することを楽しみ、「おはなし」が人生を豊かにし、時には人生の支えにもなることを感じることができます。そう信じながら私たちは活動しています。

―メンバーはどんな方たちですか。
現在のメンバーは中学生から80代までの「おはなし」好きの11人です。保育士や司書、自営業者と職業もさまざま。家族の介護をしている人もいます。色んな立場の人が集まって、無理なく気軽に暮らしの中でやれる範囲で活動しています。今年4月に仲間入りした中学生は、お母さんがメンバーで、自宅で物語を覚える声を聞いているうちに、いつの間にか先に覚えてしまうようになったそうです。「私も活動に参加したいです」と申し出があった時は本当に嬉しかったです。一気に会が若返りました(笑)。もちろん男性も大歓迎。以前参加していた男性たちが、「魔法使い」より「魔女」の響きの方が好きだということだったので、会の名称はそのままにしています。
―どのように練習されていますか。覚えるのは大変そうですが、、、。
月1回の勉強会では、それぞれが覚えた物語を語り合い、感想を伝え合いながら技術を磨いています。物語は、自分で好きなものを選んだり、メンバーから「これ、あなたに合いそう」と勧められることも。やはり覚える過程が一番大変ですが、みんな自分のペースで調整しながら取り組んでいて、どうしても覚えられない月は聞き手として参加します。
覚え方は人それぞれで、全文を書き写したり、朗読した音声を車の中や歩きながら聞いたり、家事をしながら何度もつぶやいたりと、工夫しながら一生懸命に覚えています。これを続けられるのも、「ものがたり」が聞き手に伝わったと感じる時の感動が大きいから。特に子どもたちは、キラキラした目で「それから、それから?」と、「ものがたり」の世界に入り込んでくるのが分かります。食い入るように私たちの目を見ながら、頭の中では「ものがたり」の世界を見ている。その姿を見ると、こちらもどんどん伝えたくなるのです。

―どのような活動をされていますか。
地域からの依頼に応じて、保育園や学校、福祉施設などに出向いて物語を語る「おはなし魔女の宅急便」を行っています。また、たまにイベントへの出演依頼もあり、昨年は「核兵器廃絶地球市民フェス」や「ラブフェス」にも参加してステージで語りました。そして、被爆65周年から5年ごとに開催している「平和を語るものがたり」にも取り組んでいます。この「平和を語るものがたり」では、わらべうたのグループや楽器演奏者とのコラボレーション演出も行ってきました。
どのおはなし会でも、はじめに「おはなしのローソク」と呼ばれるローソクに火を灯し、「ここはおはなしの部屋になりました」と呼びかけて、参加者に心を落ち着けてもらってから語り始めます。

―「平和を語るものがたり」について詳しく教えてください。
被爆65周年の時に、平和をテーマにした物語で構成したおはなし会をやってみたいと思い立ちました。「長崎市内で活動している私たちだからこそできる「平和を語るおはなし会」をやりたい」と提案したところ、当時のメンバーで被爆の実相を目の当りにされた方が「私もやりたかったのよ」と言って後押ししてくださり実現したのが始まりです。
その反響は大きく、被爆70周年、75周年と会を重ね、昨年11月には「核兵器廃絶地球市民フェス」でも行いました。そして、被爆80周年の今年5月、長崎原爆資料館ホールにて「平和を語るものがたりV」を開催しました。「嘉代子桜」や「字のないはがき」、「だいじょうぶだよ ぞうさん」のほか原爆や戦争、命をテーマとした全8作品を語りました。参加者の様子や感想から、平和の大切さを伝えるときに、子どもと大人が一緒に聞けて、一緒に考えてもらうことができるツールとして「ものがたり」は最適だと感じました。子どもは子どもとして、大人は大人として、それぞれの立場で受け止めて聞く。難しく複雑なテーマを、シンプルで分かりやすく伝えてくれる「ものがたりの力」を改めて教えられました。

―今後の活動について教えてください。
「平和を語るものがたりV」の開催後に寄せられた「世界中の人に聞かせてほしい」、「もっと広げて繋げていってほしい」といった多くの声を受けて、平和の物語を語る機会をもう少し増やしていければと思っています。まずは、要望を受けて、保育園や学校などの地域の場で、平和をテーマとした「おはなし魔女の宅急便」をやっていけたらと考えています。もちろん、民話や創作物語など世界各地のさまざまなジャンルの物語も語っていきます。何より、私たち自身が楽しみながら、昔からあった「語りの文化」を受け継ぎ、ストーリーテリングを通して「ものがたりの力」を伝えていければと思っています。

おはなし魔女の会
【Facebook】
https://www.facebook.com/ohanashimajo?mibextid=wwwXlfr